【超実践的手法】Web集客のプロが教える!戦略プラン7選
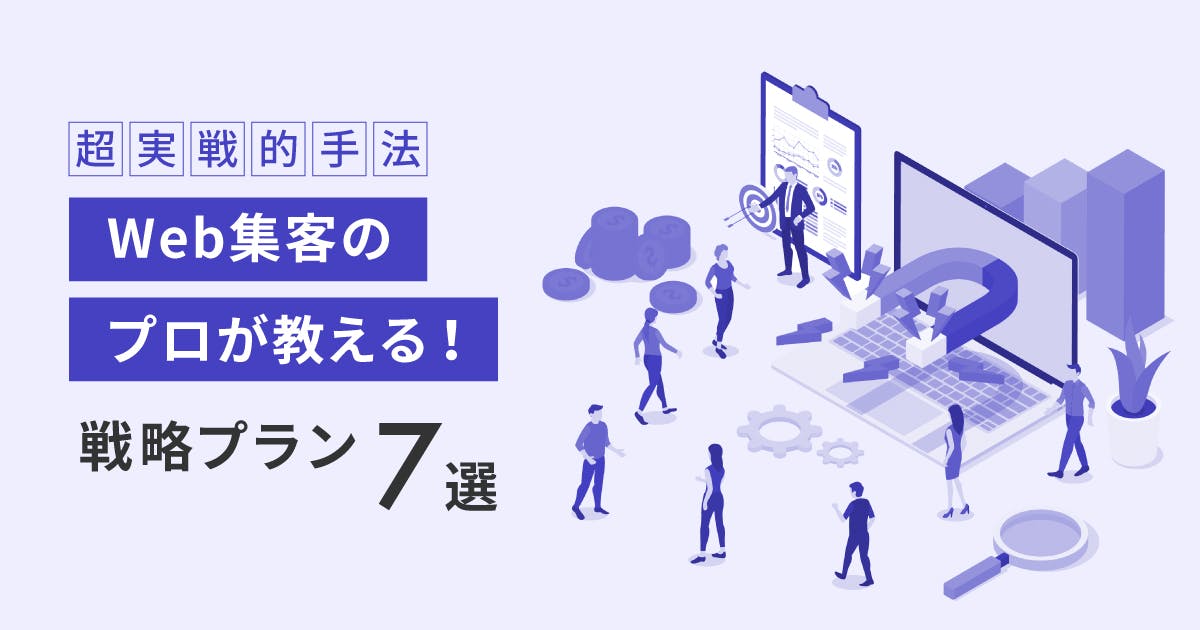
この記事では
「思うようにWeb集客ができず悩んでいる」
「Web集客を改善したいが何から手をつけてよいかわからない」といった
ビジネスをされている経営者様や事業責任者様に向けて、
Web集客のために取るべきアクションプランの全貌と、参考となるロードマップをご紹介いたします。
当社は広島市にあるWeb集客コンサルティング会社で、その他にも、自社の事業として広島市で小学生向けプログラミングスクール『スタートプログラミング』を営んでいます。
Webコンサルティングおよび自社ローカルビジネスでのWeb集客のノウハウを活かし、オウンドメディアではそれらを余すことなく読んでくださるみなさまにお伝えします。
まずはWeb集客の目的とゴールを設定しましょう。

ホームページを作ったり、いろんなWebサービスを使って情報を発信する理由はなんですか?
もちろん顧客に自社のことを知って欲しいからですよね。
ホームページなどWebを通じて集客する手段はたくさんありますが、ただやみくもにアクセスを増やしたい、お問い合わせを増やしたいでは良い顧客を集客することができません。
顧客と良好な関係を築きながら、ビジネスを成功・成長させていくのが理想だと思いますので、当社では以下の流れでクライアントと一緒にゴールを設定しています。
事業ビジョンの明確化と共有
当社では、まずお客様にどのような目的(ビジョン)があるかを共有いただいてから、ホームページおよびWebの改善をご提案するようにしています。
ホームページは企業(サービス・事業)の顔です。
ホームページを制作する会社にとっても、その事業のビジョンという芯が共有できているかで、お客様の顧客に何を提供したいかが明確になるからです。
ビジョンを共有するフェーズは、その後ターゲットを検討したり、ホームページに表現するデザインやメッセージにも影響してくる部分なので、しっかりと制作サイドと擦り合わせておきましょう。
目標数値の明確化と共有
ホームページの目的は主に以下の3つに分けられます。
ホームページの主な目的
もちろん、会社紹介やQAなど、お問い合わせを減らすことでオペレーターの作業効率化などの目的もあると思いますが、一旦ここではWeb集客という軸で話をすすめます。
目標の数値としては、例えば、毎月10件新規の顧客を獲得したい、リピーターの再購入率を10%上げたいなど、具体的な目標の数値を設定しましょう。
ただし、冒頭に書いた通り、Webのチャネルが複雑化しているため、当社の広島市の小学生向けプログラミングスクール「スタートプログラミング」でも、お問い合わせの方法もホームページやLINE・電話など経由が多様化しています。
例えば、ホームページ経由のお問い合わせの8割がスマホからが中心であれば、チャネルごとにあまり具体的に設定すると達成が難しくなりますので、注意しましょう。
ローカル(地域)ビジネスの場合は、ホームページのアクセスを増やしたところで商圏が限られるので、特にお問い合わせ(コンバージョン)が重要となります。
とはいえ、アクセスがないと検索の上位表示にもなりませんので、まずは月間1000アクセス程度を目指しましょう。
最終的には、Webトータルでお問い合わせ10件など目標数値を設定するとともに、Web改善をあの手この手で試しながら、チャネルごとに力の入れ方を最適なバランスで見極めていくという流れになります。
目標数値を達成する期間の設定
最後に、目標数値を達成する期間の設定についてです。
この目標数値はホームページをリニューアルし、少し対策すれば達成できるようなものではありませんし、そのような簡単な数値を目標とすべきではありません。
商圏エリアでNo.1になったといえるレベルの目標数値を設定すべきですし、その目標数値を達成するためには少なくても1年はかかるはずです。
ちなみに、当社のスタートプログラミングの場合、広島市というエリア内のWeb集客では競合と比べて圧倒的に強い状況を作り上げましたが、それでも現在の状況に持っていくまで紆余曲折ありながら1年程度はかかりました。
少し話が脱線しますが、当社のクライアントからはよく下記のような3つの質問をいただきます。
それぞれのご質問にお答えします。
SEO対策をすれば検索順位で1位が取れますか?
SEO対策と言ってもたくさんの手法や観点があり、一概にこれがSEO対策だというものはありません。
ホームページに関するあらゆる対策がSEO対策であり、またこの対策をしたから順位が上がるという約束されたものではないということです。
Googleの検索順位はもちろんGoogleが決めていますが、評価基準としてはユーザーの検索目的に対してホームページが高い精度で答えているか?という点をGoogle自体が明示しています。
要するに良いコンテンツをユーザーに提供することがもっとも重要視されるということですね。
ブログをたくさん書けば検索で上位表示されるようになりますか?
ひと昔前はブログやページなどをたくさん生成することで検索が上位表示されるということがありました。
前の質問で回答した通り、現在ではユーザーが悩みや疑問を持って検索した答えとしてブログやホームページがあるべきで、良質なコンテンツでなければSEO効果はほぼないとお考えください。
検索で上位表示されるようになるとお問い合わせが増えますか?
もちろん自社のホームページが検索結果に上位表示されると、ホームページがアクセスされる可能性は上がります。
ただし、ユーザーの検索意図が検索結果に表示されるホームページの概要と合っていない場合、クリックされずホームページが表示されません。
また、ホームページが表示されても、ホームページの内容がわかりづらいなど問題がある場合、お問い合わせに至らないため、単純に検索上位表示が達成できれば良いというものではありません。
ということで、「検索ユーザーが求める情報が良質なコンテンツとして用意されているか?」が検索順位にも影響してきますし、ホームページに訪問してもらったユーザーが問い合わせしたいと思うような内容にまとめるということを意識することが大事です。
競合を調査して自社のポジションを確認しましょう

ゴールを設定したところで、早速ホームページ制作やSNSのテコ入れをしようとしてしまいがちですが、実はまだやるべきことはたくさんあります。
まずは自社のポジションを確認しましょう。
当社がWebコンサルティングを依頼された場合も、もちろんご依頼の企業様のポジショニングや同業他社の現状から調査します。
調査方法など詳しくは別の記事で解説したいと思いますが、広島という小さいエリアでの集客の場合、調査する競合他社は上位10〜20社程度で十分だと思います。
競合分析・調査(キーワード・順位)
まずは簡単に業種名(例:プログラミングスクール)とエリア(広島)などの組み合わせでGoogleにて検索します。
表示された同業社のホームページを、片っ端からどんなワードやキャッチコピー(メッセージ)が使われているかをピックアップします。
また、その競合他社の中でも、自社はどのあたりのポジション(順位)にいるのかなど明確にしていきましょう。
競合コンテンツ一覧
調査した競合他社をピックアップできたら、その競合他社が制作しているコンテンツを調査します。
具体的にはどんな名前でどんなページを作っているか、発信している情報のカテゴリや粒度はどのようなものか?などです。
他社が取り入れていたり、表現しているコンテンツで良いものは徹底的に取り入れて、差別化されている箇所はつぶしていきましょう。
競合SNS調査(Twitter・Facebook・LINE@・YouTube)
代表的なSNSについて、こちらもコンテンツと同じく他社がどんなSNSで情報を発信しているか、うまく活用できているか、自社で取り入れていないメディアはないかを調査します。
Googleマイビジネス順位
Googleマイビジネスの検索順位はローカル(地域)ビジネスにおいては、現在非常に注目したいポイントです。

※ キーワード「広島 プログラミング」でのGoogle検索結果
Googleマイビジネスとは、上記のように表示されるマップに紐づく検索結果で、最近では通常のホームページの検索結果より上位に表示される枠組なので、ホームページ制作業者などでこの表示順位を非常に重要視している会社が多いと思います。
こちらも詳しくは別途記事にしますが、Googleマイビジネスの対策は今すぐにでもやるべきプライオリティの高い対策の一つです。
ホームページアクセス分析ツールを導入・設定しましょう

分析ツールが導入されていない場合はを必ず導入しましょう。
知らないうちにホームページ制作業者が設定しているケースもあるので、よくわからない方はホームページ制作業者に問い合わせることをおすすめします。
最低限以下の3つを導入・設定しましょう。
細かい設定方法や分析方法は、また別記事にて公開します。
Google Analytics
Google Analyticsとは、Googleが提供するアクセス分析ツールです。
基本無料で利用でき、登録したホームページのユーザーの行動に関するデータを分析することができます。
例えば、「サイトの訪問者数はどれくらいか」「訪問者はどこから来たのか」「使われたデバイスはスマホかパソコンか」などのデータを計測することができます。
今後、ホームページを運用し、データドリブンで改善していく時に必須なツールとなりますので、未導入の場合はすぐに導入しましょう。
Google Search Console
Google Search Console は、Google 検索結果での自社サイトのパフォーマンスを監視・管理できる Google が提供する無料サービスです。
Google Analyticsとの違いですが、Google Analyticsはホームページに訪問したユーザーがどこからきて、どのようなページを見て、どのぐらい滞在したかがわかるのに対して、Google Search Consoleでは、検索結果に自社のホームページが、どんな検索ワードで、どのぐらい表示され、どのぐらいクリックされたかがわかるツールとなります。
Google Analyticsとセットで必ず導入すべきツールですので、こちらも未導入の場合は必ず導入しましょう。
Google Tag Manager
ホームページを運用していると、Google Analyticsのような分析ツールだけでなく、Google AdwordsやYahooリスティングのようなインターネット広告を使う機会が出てきます。
これらのインターネット広告は効果測定のためホームページにタグというプログラムを埋め込まなければなりませんが、これらのタグを一括管理してくれるツールがGoogle Tag Managerです。
この記事を読んでくださっている方は、時間をかけてWeb集客に力を入れようとされていると思いますので、こちらもいずれ必要となってくるツールです。
最初に導入しておくと後々便利なので是非導入しておいてください。
分析ツールで自社の現状を詳しく把握しましょう

分析ツールを導入すると、ホームページへアクセスしたデータや、検索されているキーワードが分析できるようになります。
データ量が少ないと分析してもあまり傾向がわからないので、データを確認するには導入から最低でも1ヶ月経過してからにしましょう。
分析にはホームページへのアクセスしたデータと、検索されたキーワードのデータを使います。
これらはそれぞれ先ほど紹介したGoogle AnalyticsとGoogle Search Consoleを使います。
アクセス分析
アクセス分析には、Google Analyticsを利用します。
自社のホームページにどのぐらいのユーザーがアクセスしているのか?
どんなユーザーがどこからアクセスしているのか?
どんなページがどのぐらい閲覧されているのか?などを調べることができます。
また、広島など地域ごとのアクセスも分析できますので、ローカル(地域)ビジネスの場合にも十分に活用できます。
ホームページの目的(コンバージョンといいます)がお問い合わせだった場合は、コンバージョンの設定をすることで月次のお問い合わせの件数や、お問い合わせの確率などが分析できるようになります。
まずはGoogle Analyticsを利用して現状を把握し、今後取るべきアクションを検討していきましょう。
キーワード分析
検索キーワードの分析には、Google Search Consoleを利用します。
主にSEO対策のためのツールではありますが、Google Search Consoleを見ると、様々なキーワードで自社のホームページが検索されていることがわかります。
基本的には、
想定しているキーワードで自社のホームページが検索されているか?、
また検索のキーワードでどのぐらいの回数検索結果に自社のホームページが表示されているか?を確認しましょう。
ユーザーの検索キーワードの中には全く想定していないキーワードを発見し、思いもよらなかったユーザーのニーズを発見できることがあります。
どんなユーザーがどんな意図とニーズを持って検索しているかをキーワードから想像しながら、今後発信していくコンテンツの設計に組み込みます。
キーワード分析による課題発見・抽出、改善対策の実例を以下の記事にてご紹介していますので、よかったらこちらも参考にされてください。
【実例】お手軽ホームページ検索キーワード分析で誰でもできるSEO改善
やるべきことをリスト化してロードマップを作成しましょう
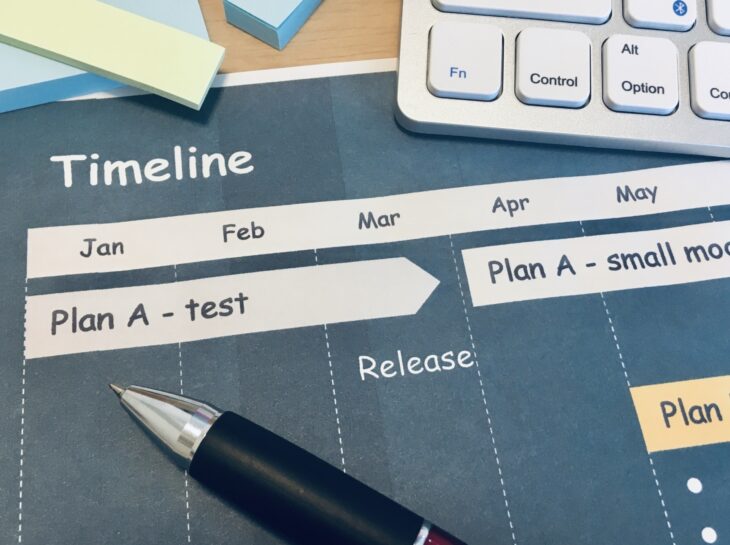
ここまでで、やっと現状分析が終わりです。
ここから課題の発見と抽出、対策とその効果測定が待っています。
だいたいこの時点で1/4ぐらいでしょうか。
ここからは、課題の発見と抽出フェーズにはいります。
自社のホームページの現在位置や競合他社との差が見えてきたところで、課題を発見して対策すべき課題を見極め、今後やるべき対策をピックアップしていきます。
次に、目標達成に向けて優先度を考えながら対策を順番に並べてください。
自社でできることできないこと、作業工数などの問題もあると思いますが、焦らず時間をかけてでも進めていくという意思が重要です。
コンテンツ設計(情報発信のカテゴリ整理)
前述で分析したGoogle Search Consoleや、Google広告が提供する「キーワードプランナー」という機能を使って、ユーザーの課題やニーズに紐づくキーワードを整理していきます。
現在の自社のホームページで説明できていない情報はページとして追加したり、細かいハウツーやノウハウはブログコンテンツとして公開するとユーザーの信頼をもらえると思います。
情報整理にはマインドマップを利用するとよいでしょう。
私の場合はXmindというマインドマップツールを使っています。
ロードマップ
ここまでで目標設定とその期間を設定してきました。
あとは設定した目標を分解し、3ヶ月程度の単位でやるべきことを検討していきます。
例えば、現状アクセスが少ないならばまずは月次で500セッションを目指す、などです。
当社の場合はさらにGoogle社やFacebook社も導入しているOKR(オーケーアール)というチームの目標管理メソッドを取り入れ、500セッションなど目標達成に向けスタッフ全員が自発的かつやりがいを持って目標達成に取り組めるようなチームビルディングを心がけています。
OKR(オーケーアール)とは?
ホームページのリニューアルを設計しよう

ここからが前述までにピックアップした課題に対する対策のフェーズです。
ホームページのリニューアルといっても、必ずしもすべてをフルリニューアルする必要はありません。
デザインを刷新して見た目をガラッと変えたいところではありますが、もっとも優先すべきはホームページに訪問してくれたユーザーにとって、必要な情報が十分にわかりやすく伝わるということです。
あるべき情報がなかったり、情報として不足・わかりづらいものがあれば整理して改善いく方がコストもかからずに効果(コンバージョン)に直結します。
一般的に広島など地域を商圏にしたビジネスにおいて、商品やサービスを紹介するホームページではユーザーは以下のようなコンテンツを求めています。
ユーザが求める情報
すべてあたり前の情報に思えますが、正確に表現できていなかったり、伝えきれていない項目はありませんでしたか?
自社のことは意外と客観的に見えてなかったりしますので、実際の顧客からわかりづらい点をヒアリングすると色々と気付かされることがあります。
ホームページに必要な技術的対策を施しましょう

せっかく良いコンテンツが揃ったホームページが制作できても、技術的に必要な対策ができていないホームページは、ユーザビリティ(ユーザーの使いやすさ、ホームページの読みやすさ)が低く結果的に検索順位を下げてしまう可能性があります。
また、ユーザーにとって読みやすい文章でも、コンピュータ(Google)にとって適切なプログラムである必要があります。
このあたりはホームページ制作業者などプロにお願いした方がよいでしょう。
最低限やるべき必須の技術対策
以下に、主な技術的な対策を列挙しました。
専門的な内容なためここでは割愛しますが、かならずやるべき対策と言っても過言はありません。
Web集客改善の流れ
- HTTPS接続
- サーバー高速化
- レスポンシブ接続
- 技術的SEO対策
- セキュリティ対策
- ユーザビリティテスト
- AMP
- CMS(WordPressなど)
ホームページ以外でのWeb集客も進めていきましょう

ホームページのリニューアルでコンテンツを見直し、技術対策を施したことでかなりの改善が図れたと思います。
このあとは変更後の効果測定と分析を繰り返ししながら、再度改善のポイントを見つけ、再び改善するという地道な作業です。
ここまで読まれた方にはホームページの改善がいかにPDCAサイクルで積み上げるものかがイメージできたのではないかと思います。
さて、ホームページの集客が形になってきたところで、次はホームページ意外のチャネルの開設や改善を行いましょう。
主なWebのチャネルや対策すべき項目を列挙しました。
Web集客改善の流れ
- 被リンク集め(まとめサイト等)
- SEO
- MEO(Google枚ビジネス)
- リスティング
- SNS(LINE@、Twitter、Facebook、Youtube)
- メールアドレス(MailChimp等)
- メルマガ(まぐまぐ等)
- Webプッシュ通知
ここで、ホームページとそれ以外のWebチャネルの改善の優先順位が気になったと思います。
当然業種ごとに異なりますが、目安として検討期間が長い当社のプログラミングスクールのような場合はホームページでじっくりと内容調査し、他社比較をするため、最終的にホームページでコンバージョンすることが多いと思います。
その場合は、ホームページの改善を優先すべきでしょう。
さらに真剣に取り組むならABテストやヒートマップツールを使って改善の質を向上する
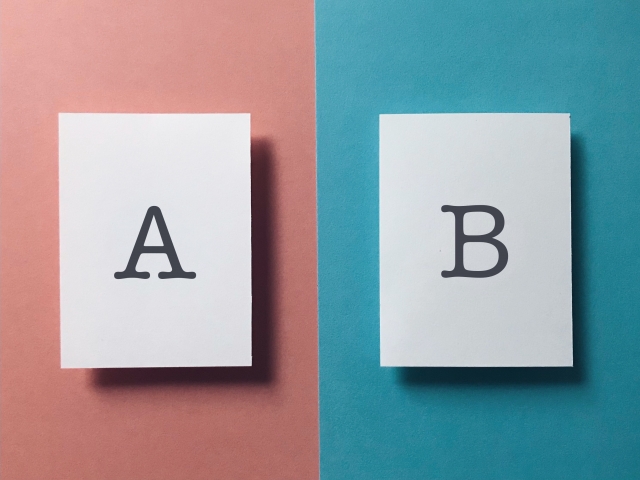
Google Analyticsなどの分析ツールを使ってホームページの課題を見つける分析を行うことができるようになると、次は改善を行うフェーズになりますがその改善の質を向上してくれるのが以下のようなツールです。
より精度の高い効果検証ができますので、また別の機会にご紹介します。
まとめ
たくさんの施策やポイントを書きましたが、Webの集客は基本的に以下の取り組みの繰り返しです。
Web集客改善の流れ
- 現状を分析する
- 分析結果から課題を見つける
- 対応すべき課題をピックアップする
- 対策を検討し優先順位をつける
- 対策を施す
- 効果を測定する
- 現状を分析する
分析して対策し、効果測定してを繰り返すだけなので、とてもシンプルです。
分析や対策の手法が多様化しているので混乱しがちですが、結局のところ発信した情報を読むお客様がわかりやすく納得してくださるかがポイントですので、困ったらまた立ち返って考えてみてください。
長文となってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
Web集客についてお悩みの場合は、是非お気軽にご相談ください。
CONTACT
お気軽にお問い合わせください。
TEL082-299-2286
NEWSLETTER
代表の佐々⽊が⽉に1回お届けするメールマガジン。
国内外スタートアップの最新情報や最新技術のサマリー、クランチタイマーの開発事例紹介など、ITに関する役⽴つ情報を中⼼にお送りします!




